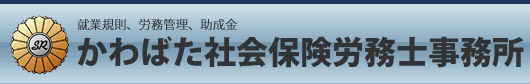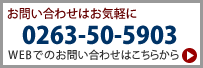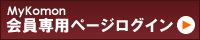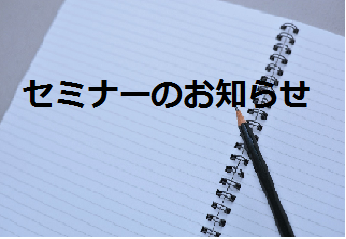平成29年度の新処遇改善加算のためにキャリアパス要件を検討する。
【全ての介護事業所が加算を算定できるために】 (2017年6月)
平成二十九年度の処遇改善加算がスタートして三か月が過ぎました。既に多くの介護事業所が四月十五日までに新しいキャリアパス要件を満たした加算の届出を済ませていると思います。
しかし、一方で、今回の新しいキャリアパス要件に対して、まだ躊躇している事業所も少なくないと聞いています。その理由は、今回のキャリアパス要件は従来のキャリアパス要件や職場環境等要件とは違って将来への財政的影響が大きいからでしょう。今回の新しいキャリアパス要件は「昇給の仕組み」を導入することです。ある程度規模が大きい事業体であれば問題ないのですが、中小零細介護事業体にとって「昇給の仕組み」を導入することは慎重にならざるを得ません。
なぜなら、今後も下がり続ける可能性が高い介護報酬制度の中で昇給のための賃金原資を毎年確保していくことは容易なことではないからです。それでは、中小介護事業体にとって、今回の処遇改善加算はあきらめなければならないのでしょうか。中小介護事業体が導入可能な「昇給の仕組み」はどのようなものなのが考えられるのでしょうか。
また、事業所の中には、十分な検討をしないまま、問題点がありながら届出してしまっているケースも少なからず見られます。ここでは、新しい処遇改善加算の要件(以下、「キャリアパス要件Ⅲ(イ)」といいます。)を再確認し、処遇改善加算Ⅰを獲得するためのヒントにしていただければと思います。
1 キャリアパス要件Ⅲ(イ)の内容
最初に、あたらしい要件の内容を確認します。
キャリアパス要件Ⅲ(イ)
介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給する仕組みを設けていること。具体的には次の一から三までのいずれかに該当する仕組みであること。
一 経験に応じて昇給するしくみ
「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること
二 資格等に応じて昇給するしくみ
「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給するしくみであること。
ただし、介護福祉士資格を有して当該事業所や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。
三 一定の基準に基づき定期に昇給を判定するしくみ
「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給するしくみであること。
ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要す。
と記載されています。さらに厚生労働省が公開しているQ&Aからは
〇昇給のしくみは、経験 資格 評価のいずれかでもよいし、それらの組み合わせでもよい。
〇昇給の方法は、基本給、手当、賞与等を問わない。
〇非常勤職員を含め、すべての介護職員が対象となり得るものである必要がある。
〇昇給の判定基準は、客観的な評価基準や昇給基準が明文化されていること
〇判定の時期は、規模や経営状況に応じて設定してよいが、明文化されていることが必要
〇加算の算定額は全額昇給に充てられる必要はない。他の賃金改善も含めて総額が算定額を上回れば良い。
という条件が記されています。
これらの条件を満たす昇給のしくみは、どのようなものが考えられるのか。以下いくつかの例を見ながら検討します。
2 昇給の判定・実施の時期の例
事業所の中には、昇給の仕組みを考えたものの、毎年度昇給するのは実際難しいかもしれないという不安から次のような規定を検討するケースがあるかもしれません。
(一)人事評価による昇給のしくみを設けたが、その判定は「業績等を勘案し、不定期に行う。」とするケース。
(二)人事評価による昇給のしくみを設けたが、その判定は「業績等を勘案し、必要に応じて行う。」とするケース。
(三)人事評価による昇給のしくみを設けたが、その判定は、「原則毎年度4月に行うが、会社都合により行わないこともある。」とするケース。
これら(一)から(三)のような規定をした場合、キャリアパス要件Ⅲ(イ)を満たすのでしょうか。
(一)は、昇給の判定を不定期に行うというものですが、これは、「定期に昇給のしくみを設けること」という条件に反しており、要件を満たさないと考えられます。
(二)は「必要に応じて行う」という内容です。Q&Aによれば、判定の時期は自由に決められますが、明文化されていることが必要とされています。「必要に応じて」というところを、どのような場合に行うか明確にする必要があります。
(三)も同様に「会社都合により行わないことがある。」という部分をどのような場合に行わないのか明確にする必要があるでしょう。使用者側が恣意的に運用できるような昇給の仕組みは要件を満たさないと考えられます。
3 昇給に業績要件をつける例
それでは、次のような場合はどうでしょう。
人事評価により毎年度定期に実施する昇給制度を設けたものの、その実施について「前年度の業績が前々年度の業績を上回ること」という条件をつけたケース。
経営状況による条件をつけることはあり得ることです。職員の処遇と経営状況を完全に切り離すことはできません。当然、この場合も条件が明確で客観的に判断できることが必要になります。この点から見て、「前年度の業績が前々年度の業績を上回ること」とする条件は客観的に判断でき明文化された条件ではあります。
しかし、前提として業績がオープンになっていることが必要ですし、事業所の実態によっては、「定期に」という条件から大きく外れる可能性があります。場合によっては、職員を失望させる恐れもあります。経営状況による留保を設けることは可能と判断しますが、職員全員が一体となって業績向上の意欲を持てるよう、その条件の設け方は慎重に検討すべきでしょう。個人的には、役職者も一般職員も同じように業績の影響を受けることには違和感があります。できれば、若年者に対しては、業績とは関係なく何らかの配慮をした昇給のしくみであってほしいと考えます。
4 昇給の対象を限定する例
次に人事評価による昇給制度を設けたものの、その対象をフルタイムの正職員のみに限定したケースはどうでしょうか。これは、「全員が昇給の対象となり得る制度であること」という条件を満たさなくなります。すべての介護職員が対象になり得ることが必要です。
次のような場合はどうでしょう。
パート、契約職員、正職員を問わず、二十代の若年者と入社後3年間の期間に限定した昇給する仕組みを導入するケース。この場合、今後、新たに入職する者は全員が対象になりますが、現に三十歳以上で既に3年を超えているスタッフが昇給の対象にならない点から要件を満たさないと考えられます。
では、次のような昇給の仕組みを定めた事業所のケースは要件を満たすのでしょうか。
「全従業員を対象とするが、同じ職位では、昇給は5年を限度とする。その後は上位の職位に昇進すれば再び昇給の対象となる。」と定めたケース。中小零細事業所にとっては経験や能力が上がったからと言っても上位のポストに限りがあり、昇進に限界があります。といって、現状の職位のまま昇給を継続することも現実的に無理という実情があると思われます。5年が妥当かどうかという議論もありますが、そもそも、中小零細介護事業所では、ポストが限られているため、職位が固定してしまいます。経験年数を重ね、能力が上がったとしても処遇できるポストがなければ現状の職務(仕事の内容と責任)を変えることができません。小規模の事業体の悩みはここにあります。筆者は、小規模の事業所は、ある程度昇給に限度があってもやむを得ないと考えています。また、限度を設けたからといって直ちに加算の要件を満たさなくなるとは考えられません。しかし、どこにどのような限度を設定するかは、事業所の状況によって区々となるはずです。また、限度を設けるならば、同時に、職員の意欲を維持するための工夫も考えておく必要があります。
つまり、中小企業の経営者は、職員の能力を上げ、その能力にふさわしい仕事やポストを与えながら事業を拡大しなければならないということです。経験や能力が上がった職員が自分の力を今の事業所では発揮できないと思った時、その職員は、他へ移って行ってしまいます。せっかく育てた能力のある職員が事業所を去っていってしまうことの無いように考えなければなりません。
5 基本給以外で昇給を考える。
ところで、昇給と言うと一般的には基本給の昇給をイメージしますが、今回のキャリアパス要件Ⅲ(イ)では、「昇給は基本給、手当、賞与等の形式は問わない。」となっています。手当や賞与で昇給のしくみを定める場合どのようなケースがあるでしょうか。
筆者は、賞与に昇給の仕組みを直接組み込むのは避けたいと考えます。理由は、賞与の固定化につながりかねないからです。基本給や手当は就業規則や賃金規定により明確に定められており、事業所としても規定に則った運用が求められます。しかし、賞与は経営者の裁量の余地が広く認められています。そこに、昇給の仕組みを直接反映させると、せっかく裁量の余地が認められ、比較的自由に決められる賞与が逆に重荷になってしまう恐れがあります。少なくとも、今回の昇給の仕組みを直接賞与の中に組み込むことは止めるべきでしょう。
6 手当を使った昇給の仕組み
次に手当による昇給の方法を検討しましょう。経験、資格、評価のどれかによる昇給でなければなりませんので、資格手当の支給が一般的と思われます。現実にすでに多くの介護事業所では介護福祉士手当を設けていると思います。
例えば、介護福祉士手当として月額1万円を支給する制度を設けていれば、それだけでキャリアパス要件Ⅲ(イ)を満たすのでしょうか。この場合、問題になるのは最初から介護福祉士の資格を持って施設に就職した者の扱いです。この者は既に資格を持っているので将来昇給するチャンスが無いことになります。厚生労働省のQ&Aでは、「他の資格取得(例えば、介護支援専門員)を条件として昇給の対象者になるようにしなければならない。」としています。仮にそうした規定にした場合、今度は、介護福祉士と介護支援専門員の両方の資格を持って施設に就職した者をどうするか定めなければなりません。仮に介護福祉士の資格をもった介護支援専門員を採用した場合は、社会福祉士の資格を取った場合に資格手当を支給するとします。そうすると今度は、介護福祉士と社会福祉士の資格をもった介護支援専門員を採用した場合を定めなければならなくなります。つまり、複数の資格手当制度を設けただけでは、要件を満たすことにならないのです。この点は誤解されている事業所が少なからず見られますので要注意です。介護福祉士手当、社会福祉士手当、介護支援専門員手当といった複数の資格手当を設けるだけで加算が取れるなら、すべての事業所がそうしています。そんな単純でないことはお分かりになると思います。
そこで、次のように少し工夫をします。介護福祉士の資格手当を月額1万円支払っている事業所で、資格取得後5年の勤続により1万5千円、資格取得後10年勤続すると資格手当を2万円に増額するという仕組みです。こうすれば、就職したときに既に介護福祉士の資格を持っている者も勤続年数を重ねることにより資格手当が増額するので、すべての介護職員に昇給の機会が担保されることになります。
あるいは、資格手当を1万円から基本給の10%のように基本給の一定割合に変更し、勤続年数が1年増すごとに.5%ずつ増加させる仕組みなどです。手当の金額を変えるしくみであれば、最初から資格を有して就職した者にも手当の増額という昇給が担保されます。
このように様々なケースが想定されま。基本給と手当の組み合わせを使えば、もっといろいろな方法が可能です。中小介護事業所にとって重要なことは、できるだけシンプルで、職員の士気が上がり、事業所の経営状況や規模、賃金制度等に合った制度を検討することです。もちろん、キャリアパス要件Ⅰとの整合性も見ておく必要があります。昇給の仕組みの導入に慎重になって加算の届出をしていない事業所もぜひ、もう一度検討していただきたいと思います。
7 届出の受付は内容の承認になるのか
ところで、既に加算の届出を済ました事業所の中には、「内容的には問題があるかもしれないが、行政の窓口からは特に指摘を受けていないので大丈夫のはずだ。」と言う方があるかもしれません。親切な行政窓口では、届出内容を精査して問題があれば連絡をしてくれるところもあるようですが、何も言ってこないところもあるようです。
そもそも「届出」という行為は行政の窓口に対して一定の内容を通知する行為です。行政が一定の基準に基づいて審査することを予定しているものではありません。形式上の不備がなく、明らかに法違反でなければ届出は受付されます。しかし、受付されたからと言って、行政が内容を全て認めたことにはなりません。これは就業規則を例に考えてみるとわかりやすでしょう。就業規則も常時十人以上の労働者を使用する事業場は届出の義務があります。しかし、届出された就業規則の全文を労働基準監督署が審査するわけではありません。あるいは、労働基準監督署の受付印があるからといって就業規則の内容が監督署のお墨付きを得たことにはならないのと同じです。処遇改善加算については、「加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない等、算定要件を満たさない場合などの場合には、既に支給された加算の一部もしくは全部を返還させることができること」とされています。後になって加算の算定要件を満たさないと言われないように注意が必要です。「加算の届出をした時には、行政の窓口からは何の指摘もなかったのに後から言われても・・・」と思うかもしれませんが、後になって加算の要件を満たしていないと指摘される可能性は十分あります。もし、既に行った加算の届出内容に不安があるようであれば早めに相談されることをお勧めします。
8 昇給が実施できなかった場合
もし、就業規則に定められた昇給の仕組みを実際に運用・実施しなかった場合、あるいは経営状況からできなかった場合はどうなるのでしょうか。中小零細介護事業体の経営者が「昇給」という言葉に身構えてしまうのは、下がり続けてきた介護報酬制度の中で賃金原資を増やしていかなければならないことがどれほど困難か予想できるからです。多くの中小零細事業所の経営者は、本当は賃金を上げたいと考えています。しかし同時に、就業規則の中で昇給を約束するのも難しいと考えています。
結論から言えば、就業規則等に定められた昇給の仕組みが仮に実施できなかったとしても、それだけで直ちに加算の返還にはならないと判断します。なぜなら、冒頭で確認したようにキャリアパス要件Ⅲ(イ)では、昇給の仕組みを「設けていること」が要件になっており、「実施していること」ではありません。実際に運用・実施していることは加算の要件にはなっていないのです。もし、就業規則に定められた昇給の仕組みが実施されていないのであれば、それは、使用者が就業規則を守っていないという労使間の問題であって、労使間で解決すべき問題であるということです。「就業規則に記載された昇給の仕組みを実施しなくても良い。」などと言うつもりは毛頭ありませんので誤解してほしくないのですが、加算の条件とは別の問題であるということです。だからこそ、「周知」については厳しくチェックをされるのです。労働基準法上の就業規則の周知は、事業所に備え付けてあれば周知したことになりますが、加算のためのキャリアパス要件を満たす周知は、全員が見ることができるような掲示や文書による通知、あるいは、回覧とともに押印で確認するなど、より積極的な周知を要求しているのはそのためです。
しかし、例えば、経営上の理由から使用者と労働者の間で話し合って合意が成立し、ある時期から昇給の仕組みを停止又は保留にしていたとします。その場合は、一旦、労使の合意の内容に就業規則を変更し、合意の時期に遡って加算を返還するよう求められることは考えられます。
今のところ、実地指導において、処遇改善加算に関していえば、「周知」と「加算の総額が全額介護職員の賃金に回っていること」の2点が中心になっており、その他については計画書等の文書の有無しかチェックされていないようです。ただし、今後はどうなるか分かりません。厚生労働省の社会保障審議会介護給付分科会の中では、「処遇改善加算によって本当に職員の処遇が良くなっているのか。」「加算の要件が甘すぎるのではないか。」という指摘もされています。今後は、キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱや職場環境等要件も含め、届出した内容が本当に継続的に実施できていることをチェックされるかもしれません。今のうちに一度確認しておくことをお勧めします。
9 個別の合意書は有効か
最後に昇給の実施に関連して次のような場合はどうでしょうか。就業規則には完璧な昇給の仕組みを定めながら、一方で職員全員から「会社が昇給を行わないことがあっても異議を唱えないこと」に合意する書面を取っている場合です。毎年昇給の判定を行うという昇給の仕組みを就業規則に規定したものの、将来何らかの事情で昇給できないような事態になった時、職員とのトラブルを避けるために事前に合意書面を取っておく方法です。
筆者はこのようなやり方は、リスクが高いのでお勧めしません。行政窓口に対しては、完璧な昇給の仕組みを定めた就業規則を提出しておきながら、一方でスタッフとは「実施しなくても文句は言いません。」という裏取引をしていることになります。実際に昇給していれば良いのですが、昇給を実施しないのであれば、その就業規則は実施しないことを前提とした虚偽の就業規則と言えなくもないでしょう。虚偽又は不正な手段により加算を得た場合は加算の返還の対象です。あるいは、使用者が「合意書」の存在を理由に恣意的に運用できるような昇給の仕組みは、そもそもキャリアパス要件Ⅲ(イ)の要件を満たしていないとして、やはり加算の返還になりかねないと考えます。
また、将来のトラブルを避けるためにと考えて職員全員から個別に合意書を取っておいても、実際にはあまり効果がありません。「未払い残業代を請求しません。」といった合意書を取っておいてもほとんど役に立たないのと同じです。このような合意書は本当に本人が自由な意思で合意しているのかが問題になります。およそ、現に在籍している職員は事業所から「合意書にサインせよ。」と言われれば、不本意であってもサインします。本当に本人が本心で不利益な内容に合意したといえるだけの客観的で合理的な事情が必要であると考えます。昇給の仕組みについても、就業規則上に記載されただけでは、個々人の賃金債権としては具体化されていませんが、意思表示の合意文書が有効か否かは、既発生の賃金債権の放棄と同様に厳格且つ慎重に判断されるべきものと筆者は考えています。
また、就業規則の規定を下回る条件での個別の労働契約は無効となり、その部分は就業規則の条件になりますので、個別に昇給の仕組みを実施しないという特約(合意の文書)を得ていても、その部分は無効になるとも考えられます。いずれにしても、あまり良い方法ではありません。
⒑ 最後に
中小零細介護事業所の経営者にとって重要なことは、一日でも早く定期昇給ができるような規模に事業を発展させることです。それが職員の幸福にもつながります。しかし同時に足元で加算を取ることも非常に重要です。「昇給はちょっと難しいから・・」と言ってあきらめず、今回の加算もぜひ全ての介護事業所がとってほしいと考えています。仮に将来何等かの事情で昇給できなくなっても、それはその時に適切な手続きで対応すれば良いのではないでしょうか。全ての事業所が各事業所の実情にあった形で加算を取っていただくよう希望します。
処遇改善加算を迷っている事業所の方はぜひご相談ください。全国対応いたします。
【参考資料】
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)
・指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)
・指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)
・指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)
・指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十八号)
・介護職員処遇改善加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(厚生労働省老健局「平成二十九年三月九日老発0309第5号」)
・平成二十九年度介護報酬改定に関するQ&A(平成二十九年三月十六日)
・介護職員処遇改善交付金に関するQ&A(厚生労働省ホームページ掲載資料)
・介護保険施設実地指導マニュアル(別冊)の改訂について(厚生労働省老健局「平成二十四年八月三十日老指発0830第1号」
・労働基準法の一部を改正する法律の施行について(平成十一年一月二十九日労働省労働基準局長通達「基発第45号」)
・第百三十一回、第百三十二回、第百三十三回社会保障審議会介護給付費分科会議事録
・シンガー・ソーイング・メシーン事件(最高裁昭和四十八年一月十九日第二小法廷判決)
退職金債権の放棄が争われた事件。この事案では、「自由な意思に基づくものであると認めるに足る合理的な理由が客観的に存在していた」と認定し、意思表示の効力を肯定した。退職後に競合他社へ転職することが明らかだったことや、在職中の旅費等経費の使用について不正の疑惑があり損害賠償を会社が求めていた等の事情が認定につながったと思われる。(労働判例百選第八版 2009年有斐閣)