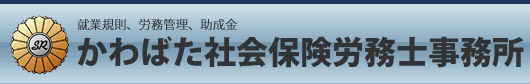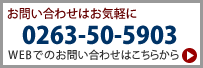労働者派遣事業を行う事業者様へ
中小の派遣事業者が労使協定方式を
選択することは本当にベストなのか?
同一労働同一賃金の中で最も面倒なのが派遣労働者です。
しかも、法律施行は2020年の4月ですので、全ての派遣元事業者はそれまでに全ての派遣労働者に対して準備を終えておかなければなりません。
パートや有期労働者は同じ会社の中に比較対象者が存在しますので、均等均衡の対応もまだ対応し易いのですが、派遣労働者の場合は、派遣先の労働者と派遣元の労働者と両者との均等均衡が必要になります。
特に派遣先の労働者との均等均衡は派遣先の情報提供という協力が不可欠です。
派遣先にとっても当然、事務処理の手間が発生します。
そんなことから、派遣元事業者の多くが、労使協定方式を選びつつあるようです。
労使協定方式であれば、派遣元事業者の内部で完結する方法ですので、派遣先からも歓迎されるでしょう。
大手派遣元事業者は当然、労使協定方式を取ると思います。派遣先ごとに派遣先均等均衡方式を取るのは煩雑な事務処理を考えると現実的ではありません。
また、大手派遣元事業者であれば、分配できる収入も大きく、労働者派遣以外にも事業を行っているケースが多く、派遣先との交渉力も強いので難しくはないでしょう。
しかし、中小の派遣元事業者が労使協定方式を選ぶ際には、そのリスクも知っておく必要があります。
●中小派遣元事業者が知っておくべき
労使協定方式のリスクとは・・・
1.労使協定方式は一般労働者の水準以上の賃金を派遣労働者に支払うことが必要です。ここで言う一般労働者の賃金水準とは、統計上の数字から算出します。
つまり、派遣労働者の業務が変わらなくても、派遣先の業績が変わらなくても、派遣契約の金額が変わらなくても、統計上の賃金が上がれば、自動的に賃金アップしなければならなくなるケースが出てくるということです。
2.労使協定方式の場合、賞与や退職金も一般労働者並の水準で支払わなければなりません。仮に、派遣先の正社員に退職金制度が無くても、派遣労働者に支払う退職金相当分を派遣先に請求しなければなりません。これは、派遣先の理解を得られるのでしょうか。
賞与についても同じです。統計上の賞与金額が上がっていれば、派遣労働者に支払う賞与相当分を増額して派遣先に請求しなければ払えません。
しかし、派遣先が「うちの会社の社員は昨年と賞与は同じなのに、なぜ、派遣労働者の賞与分を増額しないといけないのか」というケースも当然出てきます。
統計上の数字は過去のデータなので、景気の減速局面では特にこの違いが顕著になることが予想されます。
3.労使協定方式は、経験等により評価して派遣労働者に賃金を支払わなければなりません。その金額も統計的に定められています。経験の長い派遣労働者には相応の時給を支払うことになりますが、一方で、派遣先にとっては、ただ経験年数が長いだけでパフィーマンスが上がらなければ派遣料金の増額はできないと思うでしょう。
派遣元と派遣先の双方で派遣労働者の昇給に対する考えの一致がないとスムースには昇給できないことになります。
4.労使協定方式のよりどころになる統計には、職務や職務の内容や配置の変更の範囲、その他事情にふくまれるのような人材活用の違いは一切考慮されていません。転勤の有無や非常時の対応であるとか、残業要請に対応する義務の違いであるとか、正社員と派遣社員の人材活用の違いは、均等均衡の中では考慮される要素になっていますが、統計の中では一切考慮されていません。この点は、労使協定方式を取る場合には十分に注意が必要です。
5.労使協定方式は経験豊富なスキルのある派遣労働者の就業機会を奪うかもしれません。労使協定方式の場合、経験があって、スキルもある労働者は相応な時間給を支払わなければなりませんので、当然相応の業務でないと派遣できません。
しかし、そのような業務が見つからない場合どうなるのでしょうか。
派遣労働者本人が「安い賃金でも良いので、私をその業務に派遣してほしい」と希望しても、労使協定で決めた以上、本人との合意で協定を破る訳にいきません。
結局、高い賃金に見合った派遣先が見つかるまで派遣できなくなってしまいます。
(「厚生労働省のQ&A」によれば、本人の了解を得て派遣先均等均衡方式を適用することができるようです。)
5.労使協定方式が守れなくなった場合どうなるのか。
(1)労使協定を書面で締結していない場合
(2)労使協定に必要事項が定められていない場合
(3)労使協定を遵守していない場合
(4)過半数代表者が適切に選出されていない場合
これらの場合、自動的に派遣先均等均衡方式が適用されることになります。
ところが、派遣先均等均衡方式と労使協定方式では派遣先が提供する情報が異なるため、必要な情報提供がされていなければ派遣契約を締結できません。
つまり、ある日、上記の(1)から(4)に気づいた時点で派遣先からの必要な情報提供がされていなければ、派遣契約を結べないのに労働者派遣をしていたことになってしまい、違法な労働者派遣になる可能性が大です。
労使協定方式には以上のようなリスクがあることを理解して選択すべきです。
派遣先均等均衡方式、派遣元労使協定方式、どちらを選択すべきでしょうか。
<1> <2>
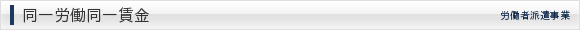
お問合せ
かわばた社会保険労務士事務所
〒390-0861
長野県松本市蟻ケ崎1丁目1-25
蟻ケ崎ビル2号
電話・FAX番号変更しました
TEL:0263-50-5903
FAX:0263-50-5904
メールでのお問合せ
sr-kawabata@office.so-net.ne.jp
〒390-0861
長野県松本市蟻ケ崎1丁目1-25
蟻ケ崎ビル2号
電話・FAX番号変更しました
TEL:0263-50-5903
FAX:0263-50-5904
メールでのお問合せ
sr-kawabata@office.so-net.ne.jp

いつでもお気軽のご連絡ください
初回無料相談実施中
長野県社会保険労務士会
社会保険労務士 川畑 潤
Mykomon会員様はこちらから
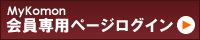
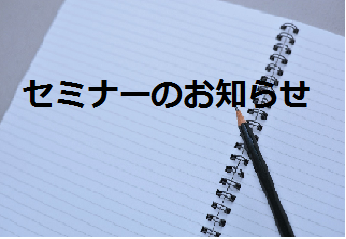
WEBセミナー推奨視聴環境
特定商取引法に基づく表示



セミナーご案内

セミナー申込み

ご依頼までの流れ

就業規則・各種規定類

紛争解決手続き代理業務

メンタルヘルス対策

賃金制度

助成金手続き

給与計算

労務監査

講習・研修

社会保険・労働保険手続き

不服申立て

リンク